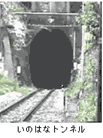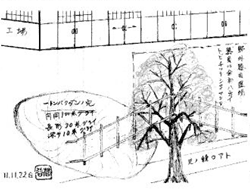|
| ||||
|
地下壕とわたし (1)
|
浅川地下壕物語(1)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (2) 武蔵野市 山口 清知さん
|
浅川地下壕物語(2)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (3) 八王子市 川村裕介さん
|
浅川地下壕物語(3)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (4) 埼玉県越谷市 峯尾 忠一さん
|
浅川地下壕物語(4)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (5) 八王子歴教協 黒坂 信也
|
浅川地下壕物語(5)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (6)
|
浅川地下壕物語(6)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (7)
|
浅川地下壕物語(7)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (8) 李 容極さん(昭島市在住)
|
浅川地下壕物語(8)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (9) 平本 清さん
|
浅川地下壕物語(9)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (10) 山辺 悠喜子
|
浅川地下壕物語(10)
|
|||
|
| ||||
|
|
浅川地下壕物語(11)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (13) 菅谷 平八郎(品川区在住)
|
浅川地下壕物語(13)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (14) 石郷岡 日出子(八王子在住)
|
浅川地下壕物語(14)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (15) 真嶋 孝士(八王子市打越町旭が丘団地在住)
|
浅川地下壕物語(15)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (16) 板倉 純(館町在住)
|
浅川地下壕物語(16)
|
|||
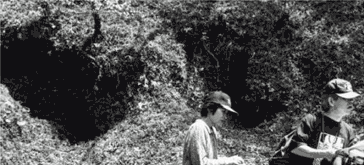 鎌田鳥山氏の地下壕入り口 鎌田鳥山氏の地下壕入り口 |
||||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (17) 岡田 祇子(八王子市在住)
|
浅川地下壕物語(17)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (19) 上野勝也(調布市在住)
|
浅川地下壕物語(19)
|
|||
|
| ||||
|
地下壕とわたし (20) 吉浜 忍(沖縄平和ネットワーク代表世話人)
|
浅川地下壕物語(20)
|
|||
 高尾町 鈴木ミヨ子さん
高尾町 鈴木ミヨ子さん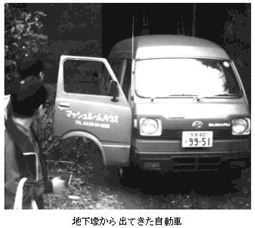

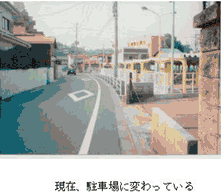
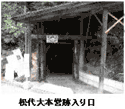 八王子市三本松小
八王子市三本松小 説明する高校生
説明する高校生 峯尾 正夫さん
峯尾 正夫さん